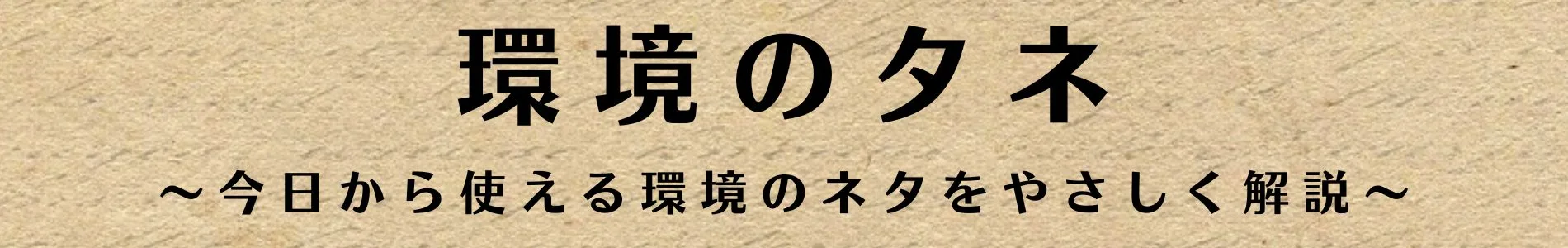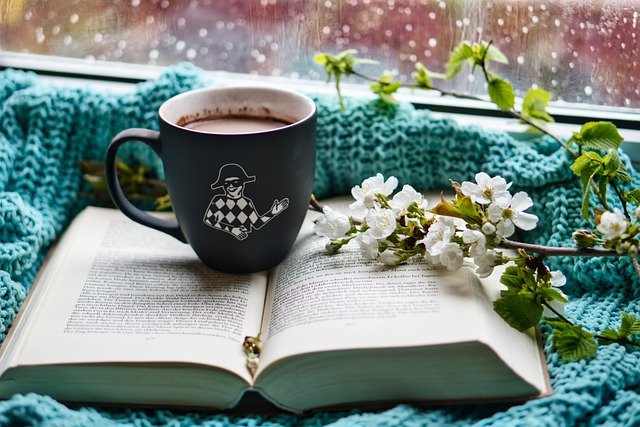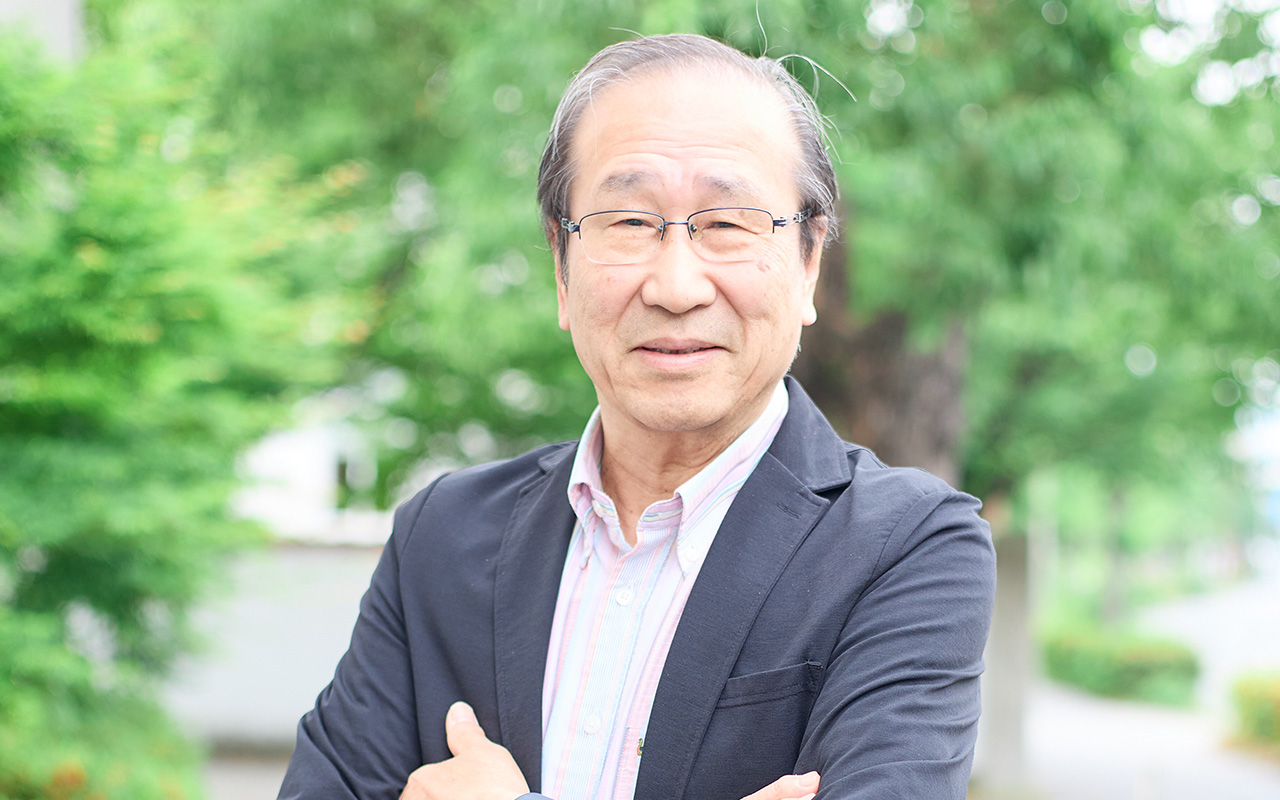毎年ノーベル賞の時期が近付くと、関連するニュースが報道されますが、「ノーベル化学賞」の候補にあがっている研究に「MOF」という用語が出てきます。
今回はMOFについて、理系でなくてもわかるようにまとめてみました。
※追記(2025年10月8日)

北川先生がノーベル化学賞を受賞しました!おめでとうございます!
※ 本ページはプロモーションが含まれています
MOFとは?
MOFとは、「金属-有機構造体(metal-organic framework)」(通称「モフ」)と呼びます。
ナノレベル(10億分の1メートル)で金属と有機物(炭素など)が合体したもの。
ポイントは、その「合体の仕方」とそれによって「得られる効果」。
これがMOFのすごいところです。
ジャングルジムのような均一な構造
公園にある「ジャングルジム」のように規則正しく合体できるんです。
つまり「構造が均一」だということ。
そして重要なのは、その骨組み(フレーム)というよりは、骨組みの間の隙間(空間)です。
この「空間が均一」であるということに非常に価値があるんです。
いろんなデザインができる
さらにMOFは、ジャングルジム以外にも、さまざまな規則正しい構造を作ることができます。
たとえば立方体や八角形のハニカム構造など、分子レベルで多様な形を設計できるのです。
つまり、MOFのメリットは、「空間のサイズや形のバリエーションが豊富」だということです。
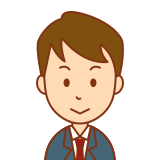
「空間が均一で、そのサイズが豊富に作れる」・・・それだと何がいいの?
「空間」の効果!活性炭よりすごい!
「活性炭」はご存じのとおり、冷蔵庫の消臭剤や浄水器などに使われているものです。
では、なぜ活性炭に消臭効果があるのかというと、活性炭の表面には無数の小さな穴(空間)があり、そこに臭いの物質が吸着するからです。
つまり、空間が多い=表面積が大きいということであり、その分だけ多くの物質を吸着できるため、消臭果が高まるという仕組みです。
そしてこのMOFは、活性炭の何倍も表面積が大きいのです。
例えば、1gあたりの表面積を比べると・・・
・活性炭:およそ800から2000㎡
・MOF :およそ7000㎡(サッカー場一面の広さ)
この驚異的な「空間の力」により、MOFにはさまざまな特徴があるのです。
MOFの特徴
空間のすごさがわかったところで、このMOFの3つの特徴をご紹介します。
貯蔵
MOFの内部空間には、水素やメタン、二酸化炭素などの気体を吸着させることができます。
水素は燃焼しても水しか発生しないため、ガソリンのように二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーとして注目されています。
しかし、水素は常温・常圧では気体のままで、液化が難しく、運搬や貯蔵の効率が悪いという課題があります。
そこでMOFを利用すれば、通常よりも多くの水素を吸着・貯蔵でき、省スペースで効率的な貯蔵が可能になります。
この性質は、水素のほか、二酸化炭素の分離回収(CCS)などにも応用が期待されています。
分離
さまざまな物質が混ざっている状態から、目的の物質だけをMOFの空間に吸着させて分離することができます。
この「空間サイズを精密に制御できる」という特長が、分離技術の分野で大きく活かされています。
ちなみに、活性炭も吸着材として利用されますが、その空間サイズは均一ではなく、さまざまな分子を同時に吸着してしまい、選択性が低いという欠点があります。
変換
MOFの内部には金属イオンが規則的に配置されており、それ自体が触媒として作用することができます。
つまり、特定の物質をMOFの空間に吸着させ、その内部で化学反応を起こして別の物質に変換することが可能です。
この技術はまだ実用化の段階にはありませんが、例えば、二酸化炭素を燃料となるメタノールなどに変換するといった応用も期待されています。
MOFの発明者
MOFの発明者は、京都大学の北川進特別教授です。
北川教授はこの分野の世界的な第一人者であり、ノーベル化学賞の有力候補として毎年名前が挙がっています。ちなみに、MOF自体はすでに1997年の時点で発見されています。
以上、MOFの特徴についてご紹介しました。
少し専門的な内容でしたが、こうした化学の力が私たちの暮らしを支える製品やサービスの根底にあることを感じていただければ幸いです。
(参考)
もっと知りたい方へ
今回のノーベル化学賞をきっかけに、「ノーベル賞」や「MOF」に興味を持った方におすすめの3冊ご紹介します。
『ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた』山口 悟 著(サイエンス・アイ新書)
ノーベル賞を受賞するような研究は、専門的で「何がすごいのか」がわかりにくいものです。
この本では、近年の日本人ノーベル化学賞受賞者の研究を取り上げ、どこが画期的だったのかをやさしく、丁寧に解説しています。
『マンガと図鑑でおもしろい!わかるノーベル賞の本 自然科学部門』うえたに夫婦 著(大和書房)
リチウム電池やワクチン、血液型の研究など、私たちの身近な便利さの多くはノーベル賞の成果から生まれています。
この本は、そんな「身の回りのノーベル賞」をマンガと図解で楽しく学べる科学読本です。
総ルビ付きで小学生から読めるやさしい内容で、大人が読んでも発見がある一冊です。
『チャンピオンレコードをもつ金属錯体最前線―新しい機能性錯体の構築に向けて』北川 進 編著(化学フロンティア)
こちらは北川進教授による専門書です。世界一のチャンピオンレコードをもつ金属錯体および研究者を紹介したものであり、化学に関心ある方は手に取ってみるのもよいかもしれません。